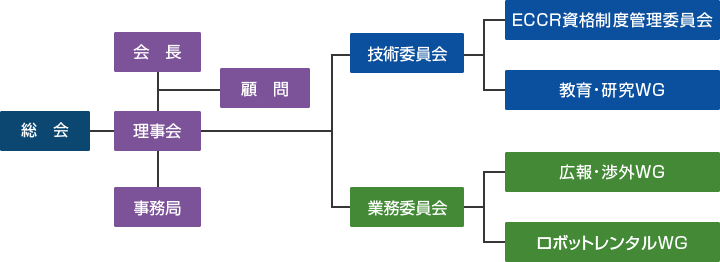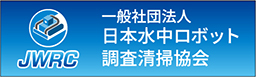協会概要
ごあいさつ
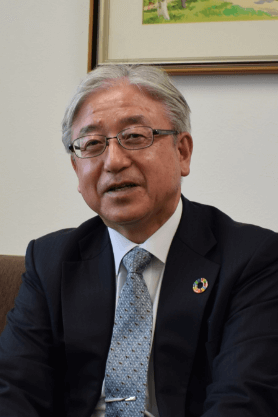
令和7年6月12日
一般社団法人 日本水中ロボット調査清掃協会
![]()
当協会は、発足以来、製造された水道水の最終ストック施設である配水池の調査と清掃を担う民間企業技術グループとして、安全で衛生的な水道水を国民に供給するという水道事業の重要な社会的使命の一翼を担ってまいりました。
令和3年度「大5回インフラメンテナンス大賞」において最高の栄誉である厚生労働大臣賞を受賞できたことは、まさに我々の活動の技術貢献度が評価された結果であると考えております。また、厚生労働省と水道技術センターの連携実施である水道の新技術事例集「Aquia-LIST」において当協会の「水中ロボット工法」が認定され、令和4年1月からホームページ上に掲載されており、さらに国土交通省の上下水道施設のメンテナンスの高度化・効率化を目的に策定された「上下水道DX技術カタログ」においても選定されて令和7年3月からホームページ上で公開されております。
当協会では、研究事業として、配水池の地震時の挙動をテーマに地震時に堆積物が舞上り、配水池が濁るという調査研究成果を日本で初めて2回に渡り発表し、調査・清掃の地震時にも備えた必要性を明らかにしてきております。従前から申し上げてあげております作業者の安全性の確保、これからの労働人口減少への対応の観点からもより一層、ロボット清掃の普及・活用が必要と考えます。
水中ロボット清掃の更なる技術向上に向けて、今年度は、2019年「水中ロボット調査清掃ハンドブックの改訂を終え、2025年版を年度当初に発刊したところです。また、令和5年3月に改訂された「水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン」(厚生労働省)からも水道施設の定期点検が休務となってきており、調査範囲の自由度がより高い水中ドローンについて昨年度に引き続き実地取扱認定の講習会を実施してまいりたいと考えております。
当協会は、令和7年度もこのような事業に取組み、住民生活の安全安心に直結する水道事業を堅固に支える事業に鋭意取り組んでまいります。

(東京都で開催)

運営組織
| 団体名 | 一般社団法人日本水中ロボット調査清掃協会 |
|---|
令和7年6月12日現在
| 協会役職 | 会社名 | 役員名 |
|---|---|---|
| 会長 | SSKファシリティーズ株式会社 | 田中 芳章 |
| 副会長 | 中里建設株式会社 | 中里 聡 |
| 副会長 | カワナベ工業株式会社 | 川鍋 太志 |
| 専務理事 | SSKファシリティーズ株式会社 | 鍋島 正憲 |
| 理事 | 浜田工業株式会社 | 嵩本 長祐 |
| 理事 | 株式会社ダイトウア | 高橋 栄吉 |
| 理事 | 株式会社髙橋工務店 | 髙橋 吉彦 |
| 理事 | 株式会社フソウ | 天崎 崇 |
| 監事 | 株式会社鹿島商会 | 遠藤 功 |
| 協会役職 | 会社名 | 役員名 |
|---|---|---|
|
最高顧問
(理事) |
元北海道大学大学院特任教授 | 眞柄 泰基 |
| 顧問 | (公社)日本水道協会名誉会員 | 川北 和徳 |
| 協会役職 | 会社名 | 役員名 |
|---|---|---|
| 特別会員 | 東京都市大学教授 | 長岡 裕 |
| 特別会員 | 京都大学大学院教授 | 伊藤 禎彦 |
| 特別会員 | 元国立保健医療科学院 | 伊藤 雅喜 |
| 特別会員 | 神戸大学大学院教授 | 鍬田 泰子 |
本部事務局
オフィス 東京・日本橋タワー
〒103-0004
東京都中央区東日本橋二丁目28番4号日本橋CETビル2階
TEL : 03‐6271-0103
FAX : 03‐6856-2861
新取引銀行口座
みずほ銀行 札幌支店 普通預金 口座番号3254618
一般社団法人日本水中ロボット調査清掃協会
沿革
-
平成13年(2001年)
「日本上水道配水池ロボット清掃協会」を正会員企業10社、特別会員1により設立 -
平成14年(2002年)
配水池ロボット清掃技術士認定証を発行 -
平成15年(2003年)
全国簡易水道協議会に入会 -
平成23年7月(2011年)
「日本水中ロボット調査清掃協会」に名称変更 -
平成24年(2012年)
定款及び細則を変更
「ロボット清掃技術指針」「水道施設調査清掃業務委託積算要領」
「ロボット清掃技士資格制度施行規程」等を作成。 -
平成25年3月(2013年)
「ロボット清掃技術指針」「積水道施設積算要領-水中ロボットによる業務編」、
「ロボット清掃技士(ECCR)資格制度施行規程」を作成した。
公益社団法人日本水道協会賛助会員(4級)に入会 -
平成26年11月(2014年)
第1回ロボット清掃技士検定試験を実施
「ロボット清掃主任技士」46名、「ロボット清掃技士」3名が合格 -
平成26年11月(2014年)
第2回ロボット清掃技士検定試験を実施
9月現在正会員企業31社、賛助会員1社、特別会員2名所属 -
平成27年4月(2015年)
設立15周年を機に、4月1日付で「一般社団法人日本水中ロボット調査清掃協会」
を設立、6月10日に「日本水中ロボット調査清掃協会」を解散して現協会へ移行
第3回ロボット清掃技士検定試験を実施
10月現在正会員企業32社、賛助会員3社、顧問1名、特別会員2名所属 -
平成28年6月(2016年)
品質安全パトロールの実施
本協会会員の施工技術の平準化と向上を目的として、
定期的に会員が施行している現場を選定し、
協会が選任したパトロール隊員による品質安全パトロールを
第1回は平成28年6月に山形県において行われました。 -
11月
日本水道協会 平成28年度全国会議で研究発表
公益社団法人日本水道協会主催、第89回 総会・水道研究発表会が
平成28年11月9日(水)~11日(金)の間、
「京都市勧業館みやこめっせ」で開催されました。
本協会は、「不断水における水中ロボットを用いた
配水池調査・清掃工法」を配水池内部の
調査・清掃工法の安全・衛生性および有効性について発表を行いました。 -
平成29年3月(2017年)
3月日本水道協会発行の「水道維持管理指針2016年版」に
水中ロボットによる不断水工法が初めて掲載
平成29年2月に公益社団法人 日本水道協会が発行している
「水道維持管理指針2016」が10年ぶりに改訂、発刊されました。
この中で、本協会が提唱する「水中ロボットを用いた不断水による調査清掃工法」について、
配水池を清掃する「水中ロボット」の説明とイメージ図が掲載されました。 -
6月
ロボット清掃技士(ECCR)資格制度の資格名を改訂
ロボット清掃技士(ECCR)資格の名称を、ロボット清掃主任技士、
ロボット清掃技士、ロボット清掃技士補から職務の基準が推測できる資格の名称、
1級水中ロボット清掃施工管理技士、2級水中ロボット清掃施工管理技士、
3級水中ロボット清掃施工管理技士に改訂しました。
(ECCR:an Engineer who has Control of Cleaning Robotsの略 ) -
10月
日本水道協会平成29年度全国会議「2017高松水道展」(展示会)に出展
一般社団法人日本水道工業団体連合会主催、「2017高松水道展」(展示会)が
平成29年10月26日(木)~27日(金)の間、
「高松市サンポート高松シンボルタワー北側広場」で開催され、
本協会は初めてブースを出展し水中ロボット2台を展示し操作説明を行いました。 -
平成30年7月(2018年)
水中ロボットの浸出試験を行う水質試験認定機関の選定
新型ロボットは協会が定める認定規定に合格すれば協会が認定する水中ロボットとなる。
認定制度の重要項目に水中ロボット本体と制御ケーブル・フロートホースを
日本水道協会が定めるJWWAZ108:2016の「水道用資機材の浸出試験」を行う事になり、
水質試験や分析に信頼のおける水質試験所を選定した。 -
8月
「水中ロボット清掃技術指針2018」を発刊
本協会が会員の技術の向上を図るため使用してきた「ロボット清掃技術指針 平成25年度版」は、
発刊されてから5年を経過していること、10年ぶりに「水道維持管理指針2016」が
改訂されたことから改訂することになりました。
本協会では改訂委員会を設置し水道技術に携わる協会員が必要と思われる知識を
できるだけ記載することとし、さらに全国で活躍している経験豊富な
「水中ロボット清掃施工管理技士」の貴重な体験を実務事例として取り入れる等、
会員が現場で困ったときに役立つ技術指針となるように5回の改訂委員会を重ね、
平成30年7月に「水中ロボット清掃技術指針2018」が発刊されました。 -
8月
地方開催の水中ロボット清掃技士技術講習会及び検定試験準備講習会
一般社団法人化されて以来、初めて地方での研修会を開催しました。
1日目(8月2日)は山形県長井市で平成30年7月に発刊した
「水中ロボット技術指針2018」を使用して講習会を行いました。
引き続き2日目(8月3日)は配水池で新型水中ロボット2台を現場で操作する現場研修を行いました。 -
8月
水中ロボット認定制度制定委員会の開催
本工法の根幹となる水中ロボットの性能基準を作成し、
その認定試験に合格したロボット(型式認定)には認定証を発行し、
公表する水中ロボットの安全性、衛生性を担保し、
本協会による水中ロボットの統一した規格として制定することとしました。
2019年4月からの制度施行を目指し、第1回制定委員会が開催されました。 -
9月
水中ロボット調査清掃ハンドブック制作委員会の開催
水中ロボット清掃施工管理技士や営業マンの必要な情報が集約された
使いやすく丈夫なハンドブックの制作が望まれていましたが2019年の発刊を目指し、
第1回制作委員会が開催されました。 -
12月
業務委託積算要領(管路等委託編)に水中ロボット清掃が掲載された。
公益財団法人日本水道協会が12月に発刊した
「水道施設維持管理業務委託積算要領(管路等管理業務個別委託編)」に
水中ロボットの積算要領が掲載されました。
また積算要領に水中ロボット清掃の業務歩掛、
解説図4水中ロボット清掃イメージ図が掲載されました。 -
平成31年3月(2019年)
水中ロボット認定に関する規定の制定
水中ロボットの安全性、信頼性および衛生面の確保を図るため水中ロボット認定委員会で
「水中調査清掃ロボットの認定に関する規定」を制定しました。
この安全、性能基準及び試験方法で行う認定試験に合格したロボットには
認定証を発行して公表します。
水道事業体には本工法への理解を深めてもらう一助となる。 -
令和元年5月(2019年)
第1回水中ロボット認定委員会の開催
第1回水中ロボット認定委員会が開催され製造メーカから協会に
提出された型式認定申請書をもとに認定委員会委員により審査を行った。
規定によるロボットの認定委員会については、京都大学大学院の伊藤教授を委員長に、
東京都市大学の長岡教授と第三の立場から日本水道協会顧問(元専務理事)の
川北先生が副委員長となり水中ロボット協会の委員が加わり審査要領の検討を行いました。 -
6月
水中ロボット調査清掃ハンドブック2019を発刊
ロボット清掃を施工する技術者が現場に携行し、作業時の注意事項、作業手順、
水中ロボットの機能点検や調査清掃時の実務事例を記載しました。
さらに業務で必要な標準的な様式集を掲載するとともに、
協会のHP会員専用ページから様式をダウンロードできるようにしました。
今後、各水道事業体への普及、啓発資料としても使用していきます。 -
6月
新型水中ロボット2台が型式認定された
水中ロボットの製造メーカは水中ロボット協会が制定した
社内検査を行った結果をまとめた型式認定申請書を作成し
協会に申請しました。
この申請書をもとに水中ロボット協会は第2回認定委員会を開催し審査を行い
性能基準、浸出試験をクリアした次の新型水中ロボット2台を型式認定しました。
1.広和株式会社製 型式 CUV-40
2.株式会社アークエンジニアリング製 型式 クリアA-1
平成28年6月~令和元年6月の沿革の詳細
組織図
(2015年12月現在)